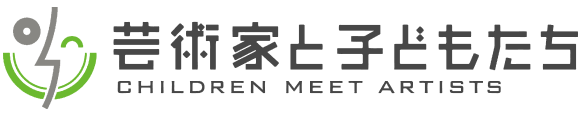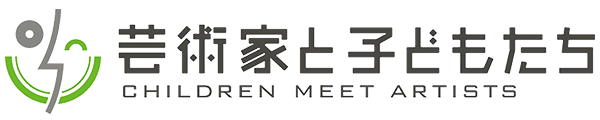障害のある子どもたちの施設・学校間交流ワークショップ ~交流会議<前編>~
芸術家と子どもたちでは、(公財)東京都福祉保健財団「子供が輝く東京・応援事業」の助成を受けて、2023〜2024年度に「障害児による創造的体験の場づくりと施設間交流によるネットワーク形成」という事業を実施しました。この事業では、障害児入所施設、放課後等デイサービス、小学校特別支援学級でのアーティスト・ワークショップと交流事業を通して、障害のある子どもたちの創造的体験や交流の場をつくり、子どもたちが健やかに成長していく環境づくりを行いたいと考えました。
そして、参加した施設職員や先生、アーティストの皆さんにお集まりいただき、取り組みを振り返るとともに、障害のある子どもたちのこれからにつながるような、ワークショップの課題や可能性について考える交流会議を開催し、お話を伺いました。今回のコラムでは、前編・中編・後編の3回にわたり、交流会議の様子をご紹介します。
※本事業の記録冊子はこちらからご覧いただけます。
事業について
今回の事業では、以下の3つの柱に沿って事業を計画しました。

違いを認め合い、互いを尊重し合うアーティスト・ワークショップの実践と、様々なレベルでの施設・学校間交流を通じて、障害のある子どもたち同士や、関係する大人たちのつながりを生み出し豊かにすることで、将来的には、障がいの有無を超え、あるいは文化的な背景や家庭環境の違い、思想信条の違いなどを乗り越えてインクルーシブな共生社会を実現することにつなげたいと考えています。

交流会議 実施概要
| 参加者 |
■障害児入所施設 進行:NPO法人芸術家と子どもたち 代表 堤 康彦、事務局長 中西麻友 |
| 開催日時 | 2024年12月27日(金)10:00〜12:30 |
| 会場 | NPO法人芸術家と子どもたち 事務所 |
| 助成 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団「子供が輝く東京・応援事業」 |
■施設同士の交流
−今回の事業では、施設同士の交流とネットワークの形成をめざして取り組みを実施してきました。普段は、どのくらい施設同士の面識や交流はあるのでしょうか。(※以下、敬称略・所属略称。)

永田(友愛)・椎名(宮代):職員同士はあまりないです。施設長同士の交流はあるけれど…。
芹澤(業平小):下校時に子どもを引き渡すとき、放課後等デイサービスのお迎えの方と少しお話しするぐらいなので、関わる機会というのはとても少ないです。放課後等デイサービスでどんなことをやっているのか、分からないことが多いです。
■それぞれの立場からみた子どもたちや施設の現状、課題
−皆さんそれぞれの立場で障害のある子どもたちと関わっていて、いろいろな課題があるからこそワークショップをやってみようと思ってくださったのだと思うのですが、現状などを教えて下さい。
若鍋(打楽器奏者):ワークショップをやっていると、子どもたちのどこに何の障害があるのかなと思うことの方が多いです。私たちは光の面しか見えていないなと思っていて、きっと大変な部分もたくさんあるのだろうなと思っています。
椎名(宮代):宮代学園は、男子寮と男女混合寮という2つの寮があって、それぞれ約15名の子どもたちが生活をしています。職員は一番多い時で、子ども15名に対して3名という比率で支援を行っていますが、どうしても介助度の高い子どもに職員の目が行きがちで、自立している子や軽度の子に対してなかなか目が行き届かないということがあり、少し寂しい思いをさせてしまっている部分もあるのかなと思っています。そういった子どもたちとの関わりの中で感じる課題は、表現方法の引き出しが少ないというところです。話すことのできる子でも、どうしてもうまく伝わらないもどかしさから、課題行動と呼ばれるような行動に発展してしまう。そういう行動が表出したときに、本人が一番苦しいと思うのですが、どうしてあげたらいいかなと私自身悩むことがあります。

始まる前に内容を子どもと相談する松岡さん
永田(友愛):友愛学園も宮代学園と同じような職員体制で、限られた職員で「余暇の確保」というのがなかなか難しい状況です。ワークショップを始めたきっかけとしては、 余暇のバリエーションが増えることで子どもたちにとって楽しい場になるといいな、という思いでした。また、児童養護施設から移ってくる子もいて、幼少期の愛着形成に課題を抱えている子が非常に多く、周りと比べるとできないことが多い子どももいます。そのような中で、ワークショップでは何をやっても「すごいね」と言ってもらえる、職員や家族とは違う外部の方から自分を認めてもらえることは、子どもたちにとって、とても大きな経験になっています。
ワークショップには入所している子どもたち全員が参加しているわけでないのですが「この子が参加してみたらどうなるだろう」「何か見つかるものがあるのではないか」という職員側の期待も少しあり、普段あまり積極的ではない子にも参加してもらっています。その中で、職員も普段の生活では見ることができないような発見もありました。ワークショップ中に突然ピアノを弾き出した子がいて「この子はピアノが弾けたんだ!」とみんなが驚いたことがありました。生活の内外でそれぞれの個性や力が発揮できるというのは非常にありがたい時間だなと思います。

相手の身体を動かしてデザインする
芹澤(業平小):ダンスのワークショップを行ったので運動面の課題をお話しすると、日々の指導の中で、子どもたちが自分の身体のイメージをもつということはすごく難しいと実感することが多くあります。また、自己肯定感が低い子どもたちもいて、自分自身の運動能力が低いこと、運動に対してマイナスなイメージをもっている子がいると感じます。否定されることなく、のびのびとやることが今一番大切なのかなと実感しています。ワークショップでは「マネキンとデザイナー」という活動をしたのですが、子どもたち同士でペアになり、相手の身体を動かしてコミュニケーションを取るということをやりました。大きく身体を動かしたり、友だちに動かしてもらったり、自分の身体を感じることができる良いきっかけになったと思います。
加藤(浮間小):自己肯定感についての話の続きになりますが、通常学級から特別支援学級に移ってきた子がいました。その子は自分を表現することが苦手で、いつも不安そうにしていました。でも、今回のワークショップで「先生、今日は生まれて初めて好きな楽器が見つかったよ」と話してくれたので、とても驚きました。コンガを本当に楽しそうに、表現力豊かに演奏してくれたのです。その子にとって、このワークショップで楽器と出会えたこと、こんなにも自分を出せたことが、良い宝になったなと思います。

好きな楽器を選んで自由に演奏する
また、私たちの学級は35人ですが、グレーゾーンの子も多くいます。自分を出せない子、情緒的にイライラしてしまう子も実は結構いるのです。ある子は、ワークショップが始まる1時間前から夢中でドラムを叩いていました。ワークショップでは自分が活躍することができるので、その空間に満足して自己肯定感が高くなり、日常生活でも少し落ち着きが出てきました。そうやって子どもを輝かせていただけたことが本当に嬉しかったです。
大塚(てくてく):やはり子どもたちが成長するためには、経験がすごく大事だと考えています。障害のある子どもたちは、経験不足や経験できないことがある中で、このようなワークショップは大切だと思っています。また、いま「地域交流」ということが放課後等デイサービスに求められているのですが、当事業所としては職員以外の外部の方と接する機会というところで、地域交流も担ってもらいたいと思っています。

つくった「チャフチャス」を紹介する
ワークショップでは、自分の作品をみんなの前で発表して「すごいね、できたね」とみんなに褒めてもらえる機会をつくってくれました。このような機会はなかなかないですし、それを見て、子どもたちも自分の作品を持って積極的に発表していました。作品に性格が出るというか、ダイナミックなものをつくる子もいれば、細かく自分なりに色を変えている子もいて、さまざまな子どもたちの一面を見ることができたと思っています。
冨田(とことこ):いま、放課後等デイサービスには、「五領域※」を含めた子どもたちへのよりきめ細かい多面的な支援が求められていています。例えば、言語や人間関係、運動とか生活、健康、そういうところを網羅した療育を放課後等デイサービスでもやりましょうということになっているのですが、日頃の課題としては、やっぱり「放課後」は短いなと思います。子どもたちは学校で一生懸命頑張ってきた後にやって来て、疲れていては何をやってもだめなので、楽しいと思って参加してもらえる、悩みを抱えている子が落ち着ける時間を、行政のガイドラインとすり合わせながらどうつくっていくのかが、難しいところです。
※5領域:「①健康・生活」、「②運動・感覚」、「③認知・行動」、「④言語・コミュニケーション」、「⑤人間関係・社会性」
日々、障害のある子どもたちと向き合っている先生や支援員の皆さんからお話を伺うことで、それぞれの現場の課題が見えてきました。また、その課題に対して、ワークショップがどのように対応できるかも分かってきたように思います。中編では、そのワークショップの様子を詳しくお伝えします。
編集:北沢理美/写真:金子愛帆
※無断転載・複製を禁ず。