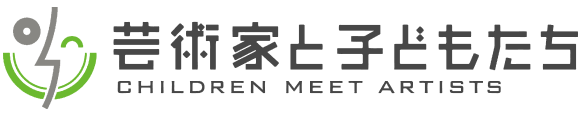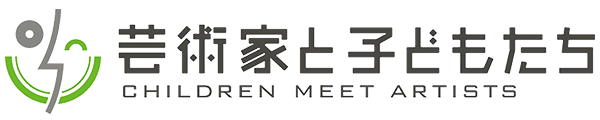障害のある子どもたちの施設・学校間交流ワークショップ ~交流会議<中編>~
前回のコラム『障害のある子どもたちの施設・学校間交流ワークショップ ~交流会議<前編>~』では、子どもたちや施設の現状や課題などを伺いました。中編では、取り組んだワークショップの様子を詳しくご紹介します。
■アーティストの気づき、感想
−施設職員や教員の皆さんからワークショップのいいところをたくさん挙げていただきましたが、アーティスト側としてはどう思っていたのか、難しかったところなども聞かせてください。

優しい音色のカリンバ
若鍋(打楽器奏者):通常の学級でワークショップをすると、子どもたちから「自由にやる」というのを引っ張り出すのが難しいことがあるのですが、特別支援学級では私が子どもたちに教えてもらっていて「そんな楽器のやり方あったの?」みたいな。子どもたちが面白い音を聞かせてくれて、私にとっても発見がとてもたくさんありました。
いつも「すごいなあ」と思って、子どもたちを見ています。「エネルギーが溢れている子」と、みんながいろいろな音を出している中にいるのがあまり好きではない「もっと繊細に音を扱いたい子」、この2つのタイプの子がいるなと感じています。エネルギーが溢れている子は、私が一緒に演奏するだけで自然に楽しんでくれるので、もっと繊細に音を聞きたいタイプの子たちをどうやって輝かせようかなというのを意識していました。
鈴や鉄琴のような繊細な音の楽器を選んだ子たちは、「水」をテーマにした即興セッションの中で、キラキラとした音を響かせてくれました。驚いたのは、さっきまで目一杯に楽器を鳴らして大きな音を出していた子どもたちも、繊細な音が出るバチを「こういうのもあるよ、ここに置いとくね」と言ったら、そのバチでちょっと擦って小さな音を出していて、みんなの耳が繊細な音に引き寄せられた瞬間がありました。
松岡(舞踏家):今回、アーティスト側にもすごく学びになったのではないかなという部分があります。 私はいろいろなところでワークショップを行いますが、他のアーティストがどんなふうにやっているのかあまり知らない。それが何年も続くと、ワークショップにはそもそも正解がないので、うまくいっているのかどうか、分からなくなる。今回の取り組みを通して、他のアーティストがどのようにワークショップをしているのか見ることができたので、とても良かったなと思っています。提案も含めてなんですけれども、例えば新たなアーティストが学校や施設にワークショップに行くときは、その一歩前の段階で、他のアーティストのワークショップを見学するとか、現場に同行させてもらうと、また違うつくり方ができるのかなと思いました。

先生たちも参加する青木尚哉さんのワーク
今回、交流ワークショップでご一緒した青木尚哉さん(振付家・ダンサー)は、先生を巻き込むところや青木さん独自の存在感があって、軽妙なトークが印象的でした。なんというか、先生と生徒のような関係性にどうしてもならないのですよね。それは外から見ていて、アーティストの良さだなと思っています。教える、教えられるというような関係性になってしまうと、それはあまり意味がないのではないかと思います。その辺の偶発性や関係性というのを意識として持つというのは、アーティストにとって共有できることなのかなと思います。
中西(NPO):今回の交流では、Zoomを使ったオンラインと、どちらかの施設や学校に出向いていく対面の両方がありましたね。
松岡(舞踏家):Zoomは意外と可能性があるなと思いました。コロナが流行していたときに、仕方なくZoomで行うということがありましたけれど。車椅子で外に出られないとか、そういう方ももしかしたらいるかもしれない。今後、積極的に活用していくことができるのかなと思いました。
また、ダンスのワークショップというと、どうしても「踊る」や「踊りを教える」ということになりがちなのですが、子どもたちの中で「表現すること=ワークショップ」になっているように感じました。ワークショップでは自由に表現して良い、それは別にダンスじゃなくても良いとなっていて、その在り方はとても素敵だなと思いました。

宮代学園のみんなが描いた舞台美術
中西(NPO):そうですね。ワークショップでは、絵を描く子や、衣装を手づくりする子もいましたね。
松岡(舞踏家):やっぱり「自分が期待していることを超えた何かが生まれる」というのが、アーティスト側にとってもメリットというか、良いことなのだろうなと思いながら、日々関わらせていただいています。
■交流ワークショップでの様子
−今回の取り組みでは、施設同士や学校同士の交流を取り入れたことが新しいチャレンジでした。交流ワークショップでの気づきや感想を教えて下さい。
中西(NPO):業平小学校は対面で、浮間小学校はオンラインでそれぞれ交流しました。
芹澤(業平小):やっぱり子どもってすごいなと思うことがありました。私はとても緊張しやすいので、初めてのところに行って、初めての人に話しかけたり、一緒に運動したりとか、不安な気持ちになるけれど、子どもたちはのびのびと過ごしていました。自分たちがやってきた活動を他の子たちに伝えてあげるとか「こうやるんだよ」「一緒にやろう」という声かけが自然に出るなど、いつものクラスの中で関わるのとは別の姿を見ることができて、すごく良かったなと思いました。また、決められた振付をするということではなくて、自由に身体を動かす楽しさを実感できたように思います。それは、子どもたちに「ちょっとできそうかも」「活動をやってみたいな」という気持ちが生まれたからではないでしょうか。合わせるのが難しいと松岡さんがおっしゃっていましたが「なんだか、みんなができそう」という気持ちが芽生えて、そこから発展させていく、というやり方が良かったなと感じました。
加藤(浮間小):オンラインで交流しましたが、やっぱり「直接行って、顔を見合わせてやりたかったね」という教員の声は多く聞かれました。音楽をオンラインで流して、交流先の学校がそれを踊っているということは、子どもたちもある程度分かるのですが、やはり距離があるので、一緒にやったという感覚は少し薄いように思います。それでも一緒にやっているというのは分かったと思うので、同じ場所にいたらもっと違う交流ができたかなと思うところはありました。

若鍋さんの合図に合わせた合奏を聴いてもらう
若鍋(打楽器奏者):画面越しだと、ワークショップで使う布の質感とかが分かりにくい。黒い人影と、青い帯状のものがはためいているな、くらいですよね。でも、実際に目の前にあると、布の軽さとか手触りとかが分かるので、そういうものが音にすごく影響する。イメージに直結するので、対面だったら、たぶん子どもたちもすっと入って音が変わっただろうなと思います。
また、最初に相手の学校が演奏を発表してから、その演奏に合わせて一緒にダンスをしてもらうという流れにしたのですが、発表したことの良さがあったと思います。せっかく演奏したものを誰かが聞いてくれるというのはめちゃくちゃ大きい。
本番でいきなりバチを上に投げるようなパフォーマンスが現れて、やっぱり本番になると子どもたちのスイッチが入るなあと思いました。見てくれる人がいて、向こうも「すごい」と言ってくれて。そういうことができたのは良かったなと思います。音楽には、例えばギターの弾き語りをしたり、ピアノを弾いたり、一人で完結できる面もあります。でも、私が音楽で一番良いと思うところ、好きなところは「たくさんの出会いがあること」だと思っています。いろいろな人と演奏して、自分との相性も含めて「この人はこういう人なのだな」というのが分かって、どんどん輪が広がっていっていく。それが、音楽をやめられない魅力のひとつだと思います。
加藤(浮間小):今回はワークショップを3回やっていただきましたが、アシスタントの方が毎回いろいろな楽器を持ってきてくれました。素敵なアーティストが来てくれて、みんな嬉しそうにしていました。

トロンボーンに挑戦する子ども
若鍋(打楽器奏者):私にとっても、かなりの挑戦でした。私はクラシックの打楽器出身なのですが、昨年までは同じくクラシックの打楽器奏者にアシスタントをお願いしていました。でも、別の企画でボーカリストの方と一緒に組んでワークショップをするようになって「世界が広がって楽しい!」と私自身が思うようになったのです。それから、自分ができないことをやってくれる方にアシスタントをお願いするようになりました。今年度はかなり幅を広げて、アコーディオンやトロンボーン、ピアノをお願いしました。それが子どもたちの性格にどこかフィットする感じがあって、私もおもしろかったです。
中西(NPO):放課後等デイサービスと障害児入所施設では、オンラインでワークショップを実施しました。入所施設では移動できそうな子どもたちと交流先の施設に出かけて、一部だけでも対面で実施するという案もあったのですが、距離の問題もあり、結局オンラインでの実施となりました。でも、先ほども話があったように、実はZoomにも意外な可能性があって、子どもたちはZoomだと画面をしっかりと見る傾向があるのですよね。

始まる前の接続テスト
椎名(宮代):子どもたちは意外と集中して画面を見てくれていましたが「画面に写っている子たちは誰なのだろう?」と疑問に思っている様子もありました。でも、お互いのダンスを発表した後に、どちらかが音楽をかけたらダンスが始まって、真似っこし合うということがありました。「Zoomでもこんなに交流できるのだな」と実感しました。
今回はオンラインでしたが、今後交流する機会があるのであれば「宮代学園の子たちを友愛学園に連れてくのもいいね」「特別感もあるし、どういう相乗効果が生まれるのだろうね」という話を他の職員としていました。
永田(友愛):友愛の子どもたちも、Zoomで宮代学園の子どもたちを見て「誰なのだろう?」と思いながら、お互いに真似し合っていたと思います。宮代学園の子どもたちがワークショップでティッシュを使っていたのを見て、友愛の子どもたちも終わった後もティッシュで遊んでいました。子どもたちは、ティッシュを使った遊び方が新しい発見だったようです。

足を使ってティッシュを受け渡してみる
中西(NPO):音楽だと通信環境による音の問題があり、ダンスは直接のふれあいを大事にするので、オンラインでワークショップを実施することに対してアーティスト側にも抵抗があるのではないかと思っていました。本当にちゃんとできるのかなと私自身も自問自答しながらの実践でしたが、子どもたちの方がはるかに軽やかに、そういう心配を超えて参加してくれていました。
交流については、放課後等デイサービスが一番心配だったかもしれません。曜日ごとに通う子どもたちが違うので、ワークショップに参加できる回数が少ない子もいます。「とことこ」と「てくてく」では活動時間も少し異なるので、より短い時間で行う必要がありました。
冨田(とことこ):心配もありましたが、子どもたちがどのように反応していくのかを見てみたいという気持ちの方が強かったです。子どもたちは、後ろからさっと出てきて、自分から前列に並んでいました。楽器をつくったことで音を鳴らす楽しさを知ることもできたと思います。自分の動いている姿が画面に映っているのを見て、楽しいと感じて表現しているようでした。

画面越しに一緒に踊る
最後に交流先の広尾てくてくの子が「私も何か言いたい!」と手を上げて、「私は〇〇です」と名前を言ってくれました。それに答えるように、こちらの子どもたちもマイクに近づいて、自分の名前を大きな声で応えていました。やはり「コミュニケーションを取りたい」「私のことを知ってほしい」という気持ちが最後に現れていたなと思います。最後には、友だちになれたのではないかなと思いました。
大塚(てくてく):ダンスと美術という異なるジャンルでどう交流していくのか、最初は心配でしたが、実際にあのような場を持てたというのは、すごく良いことだなと思いました。ワークショップでは「チャフチャス」というアンデス地方の楽器をつくったのですが、いろいろな種類の材料を用意してくださって、そこから自分の好きなものをどんどん選び取って、本当に個性豊かな作品ができ上がりました。誰のものにも似てない、ふわふわの毛糸がたくさん付いているものや、蛍光色が多く使われているものなど、子どもたちの好みが分かりました。

カラフルな「チャフチャス」
また、交流をより良くするのであれば、 ワークショップで楽器をつくっているときからオンラインでつないで「こちらではこういうのをつくっているよ」とか、お互いの取り組みを知る機会をもう少し増やしても良かったのではないかという意見がありました。
参加者の皆さんのお話を伺い、ワークショップ中の子どもたちの生き生きとした様子が伝わってきました。後編では、今後の活動に向けて、ワークショップの可能性について考えていきます。
編集:北沢理美/写真:金子愛帆
※無断転載・複製を禁ず。