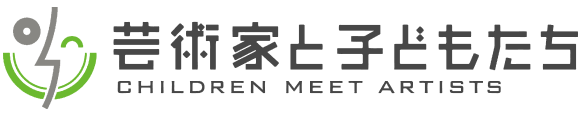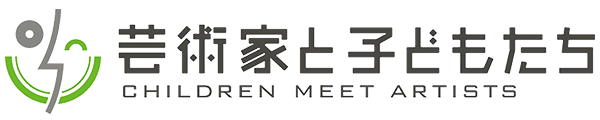障害のある子どもたちの施設・学校間交流ワークショップ ~交流会議<後編>~
前回のコラム『障害のある子どもたちの施設・学校間交流ワークショップ ~交流会議<中編>~』では、ワークショップの様子や、参加者の気付きなどを中心に伺いました。後編では、今後に向けての可能性を考えていきます。
■つながりをつくるということ
中西(NPO):私たちはいろいろな場所でワークショップを実施していますが「つながりをつくる」ということのきっかけは、児童養護施設でした。基本的には施設ごとに関わっているけれど、アーティストからの提案もあり、施設同士が一緒にワークショップをしてみるのも良いのではないかと思ったのです。つながりを持つことが、少しでもプラスになったらいいなという思いから、交流のあるワークショップを始めました。最近では、特別支援学級と通常級の「交流及び共同学習」に関わる機会もあり、交流するワークショップの良さを感じています。今回の企画では、人と人とのつながりをどうやって築くかを考え、施設同士や学校同士での交流ワークショップをしてみることにしました。
堤(NPO):最初は学校教育の現場でたくさんワークショップをやっていましたが、児童養護施設での活動をきっかけに、今は福祉の現場での取り組みが増えてきています。なんとなく感じるのですが、子どもたちよりも、そこに携わっている先生や職員の方々の間に、教育と福祉の異なる世界観があるのではないかと思っています。学校(教育)の場合、特別支援学級の場合はそれほどでもないのかもしれないけど、成長や学びが段階的に上がっていくことを目指しているように思います。
福祉の場合は、もう少し日常生活の中で個々の豊かさを求めているような気がします。教育と福祉を専門的に勉強したことはないのですが、現場でいろいろとお話を伺う中で、なんとなく感じているところなのです。ただ、子どもたちの過ごしている日常は、教育も福祉も一緒なのではないかと思っていて、教育と福祉の人たちがもっと越境して活動したら、なにか面白いことがあるのではないかなとちょっと感じているところです。私たちのようなNPOで第三者的な立場だから、気軽に言えるのかもしれないですけれど。
大塚(てくてく):日々の支援の中で、地域連携が重要視されています。支援者会議を定期的に行うというのが本来というか理想の姿だと思うのですが、実際にはなかなか難しい状況です。先ほど堤さんも言っていた、教育と福祉との違いというのもあります。 語弊があったら申し訳ないのですが、やはり学校は「指導」が重視されているように思います。一方、福祉では「支援」という言葉が使われており、法律も違います。
また、学校では学習指導要領の中で、おそらく一年間で取り組まないといけないことが決まっていると思います。放課後等デイサービスに関しても、ガイドラインがありますが、それぞれの違いによる難しさがあるのかなと思います。
堤(NPO):特別支援学校や特別支援学級というのは、学校文化の「指導」と福祉文化の「支援」をつなぐものになり得る、なんだか面白い、良いポジションなのではないかなと思いました。
中西(NPO):地域連携ということで、子どもに関わる人たちが情報共有をしていくことが重要で、異なる場所でバラバラに支援するのではなく、ひとりの子どもをしっかりと支援するためにつながっていこうという方針を今、実現しようとしているところですよね。口で言うのは簡単だけれど、場所によって活動の時間帯や関わる人も違うし、大変だろうなと想像します。

みんなで輪になって踊る
■ワークショップへの期待と可能性
−最後に、これからのワークショップに対しての期待や、こういうワークショップをやってみたいという要望など、ありますでしょうか。
冨田(とことこ):アーティストが来てくれたことによって「ダンスをやりたい」とか「楽器をやっていきたい」とか、やりたいことが見つかった子は、本当に幸せだと思います。子どもたちは18歳までしか放課後等デイサービスに通うことができなくて、親御さんたちから今後の不安をよく聞きます。成人になったときに、青年サークルみたいなものが少しずつできて、「あそこ行って何か教えてもらいなよ」とか「何かできるよ」というふうに言えたら良いなと思っています。
大塚(てくてく):経験が少ない子どもたちが多く、体験の場へ連れて行けない保護者もいらっしゃいます。そうした中で、アーティストとのふれあいや、自分を認めてもらえるワークショップというのは、とても良い機会になっていると思います。子どもたちが好きなことや集中できること、夢中になれることを見つけて、それをこちらから情報共有することで、保護者にとっても新たな発見になっていると思います。子どもたちの将来や、今後の余暇などにつながっていけると良いなと思います。
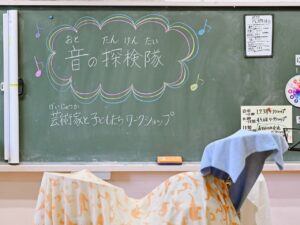
先生が描いてくれた黒板の掲示
加藤(浮間小):本物を子どもたちに味わってもらいたいといつも思っています。学校でよくスクールコンサートとか劇団に来てもらうこともありますが、子どもにとって一方的で、一回聞いたら終わりということが多い。でも、このワークショップは、アーティストやスタッフが学校に出向いてくれて「どんな形でワークショップをやりましょうか」というところから始まるのが、素敵なところだなと思っています。そして、終了後には振り返りもしてくださって「次はこうしてみよう」とみんなで考えて、積み重なっていくところが良いなと思います。また、特別支援学級の子は、何度も繰り返し体験できることや、同じアーティストが来てくれるということに魅力を感じるようです。積み重ねのありがたさを実感しています。
芹澤(業平小):学校同士やいろいろな関係施設など、ワークショップを通して人と人とをつなぐきっかけをつくってくださっているのが一番ありがたいなと思っています。学校の外に出るとか、学外の交流というのは、価値はあるけれども、向こう側との折り合いをつけなければいけないとか、なかなか踏み出せないところもありました。今回の機会で子どもたちも成長したと思うし「次はこんなことをやってみたい」というような意見も出ています。
また、加藤先生もおっしゃっていた通り、このワークショップは一方的ではなくて、子どもたちが自分自身の中に持っているものを引き出してくれます。大人が提供したものではなく、自分で「楽しい」を見つけるとか、つくり出すことができる。この経験がすごくありがたいなと思っていて、これからも継続して続けていきたいなと思います。

一人ひとりと関わりながら踊る松岡さん
永田(友愛):ワークショップの日、子どもたちは朝から「松岡さんが来る!松岡さんが来る!」というように楽しみにしています。アーティストだけではなくて、事務局スタッフの名前も覚えていて、それぞれが「推し」を決めているような感じです。本当に皆さんが来られることを楽しみにしているなと感じています。
また、余暇の時間に何をするのか決められない子はたくさんいます。ワークショップでは、自分の好きなもの、自分の能力とかが花開くときがあるので、そういうものが見つかると、きっと子ども自身の将来の生活でも強みにはなっていくのだろうと思います。
椎名(宮代):ワークショップでのアーティストとの関わりや、子どもたちが自由に表現して、それを受け止めてくれる場というのは、私たち職員にとってもプラスの面をたくさん見ることのできる、大切な時間だなと思っています。

つくった衣装を着て踊る
先日、保護者の方に少しお話を伺う機会がありました。そのお子さんは人見知りが激しくて、学園ではなかなかおしゃべりができないのですが、ワークショップを始めたくらいから「とても明るくなりました」とお話してくださいました。その子は、私に対しても話しかけてくれることが少なかったのですが「椎名さん、今日はこれを頑張ったよ」と言ってくれることがすごく嬉しくって。やはり日常生活の中にも良い影響、成長につながっていのるかなと実感しています。
若鍋(打楽器奏者):私は小さいときに打楽器が好きになって、そのまま大人になって。ひたすら好きなものだけをやってきました。多分これからもそうですけれど。でも、ひとつ好きなものが見つかると、やっぱり強いなと思っていて。もし打楽器をやっていなかったら、今の人生ではないし、考え方も違っていたと思います。皆さんの「こういうことをやって欲しい」という希望を聞いて、私ももっとおもしろいことやりたいなと思っています。

太鼓を叩いて赤くなった手を見せてくれる子どもたち
松岡(舞踏家):今回、複数のアーティストが関わることで、いろいろな発見がありました。今後、例えば、ひとつの施設の中で、複数のアーティストが受け持ちながら何かつくるというのも面白いのかなと思いました。
また、この取り組みの「セクション(施設)を越えて、つながりをつくる」というところを、もう少し社会に発信できないのかなと思います。普通の人は、たぶん知らない。それが、障害のある方が隔離されてしまうとか、自分の好きなことに向き合えないということにつながっているのかなと思っていて、もっと知ってもらうということが、 活動の中にあっても良いと思っています。
■今後について−お互いを理解するために大切なこと
中西(NPO):事業が始まる前は、私たち自身も大丈夫かなと心配していたのですが、何よりも子どもたちのおかげで、そして皆さんの多大なご協力があり、無事に実施することができました。でも、障害のある子どもたちをめぐる世の中に対して、どうにかしていかなきゃいけないこととか、私たちができることはまだまだあるなと改めて思ったので、今回の気づきや学びを今後に活かしていきたいです。

交流会議に参加してくださった皆さんと
堤(NPO):いわゆる「健常の子ども」と「障害のある子ども」のつながりというか、お互いが理解し合えるような雰囲気を醸成していかないといけない。本当の意味でのインクルーシブな社会というのをつくっていくにはどうしたらいいのか、同時に考えていきたいなと思っています。私たちは障害のある子どもたちの良さというか、面白さ、能力、そういうものを感じているのですけど、それが社会になかなか伝わらない。 だから、もっとパイプを多くするとか、実際に出会う機会を多くするとか、そういうことがきっと必要なのだろうなと改めて思いしました。今日は本当にありがとうございました。
今回の取り組みは、施設や子ども同士の交流を取り入れた試みでした。自由に表現することの楽しさ、心が満たされて変化していく気持ち、好きなことを見つけたときの喜び。しなやかな心でお互いを感じ合いながら交流している子どもたちの姿を見て、大人たちもたくさんの気づきを得ることができました。「つながりを持つ」ということは、他者と関わることで自分を再発見することができる大切な機会であると思います。今後も、さまざまな場所や人のつながりを生み出していきたいと考えています。
編集:北沢理美/写真:金子愛帆
※無断転載・複製を禁ず。